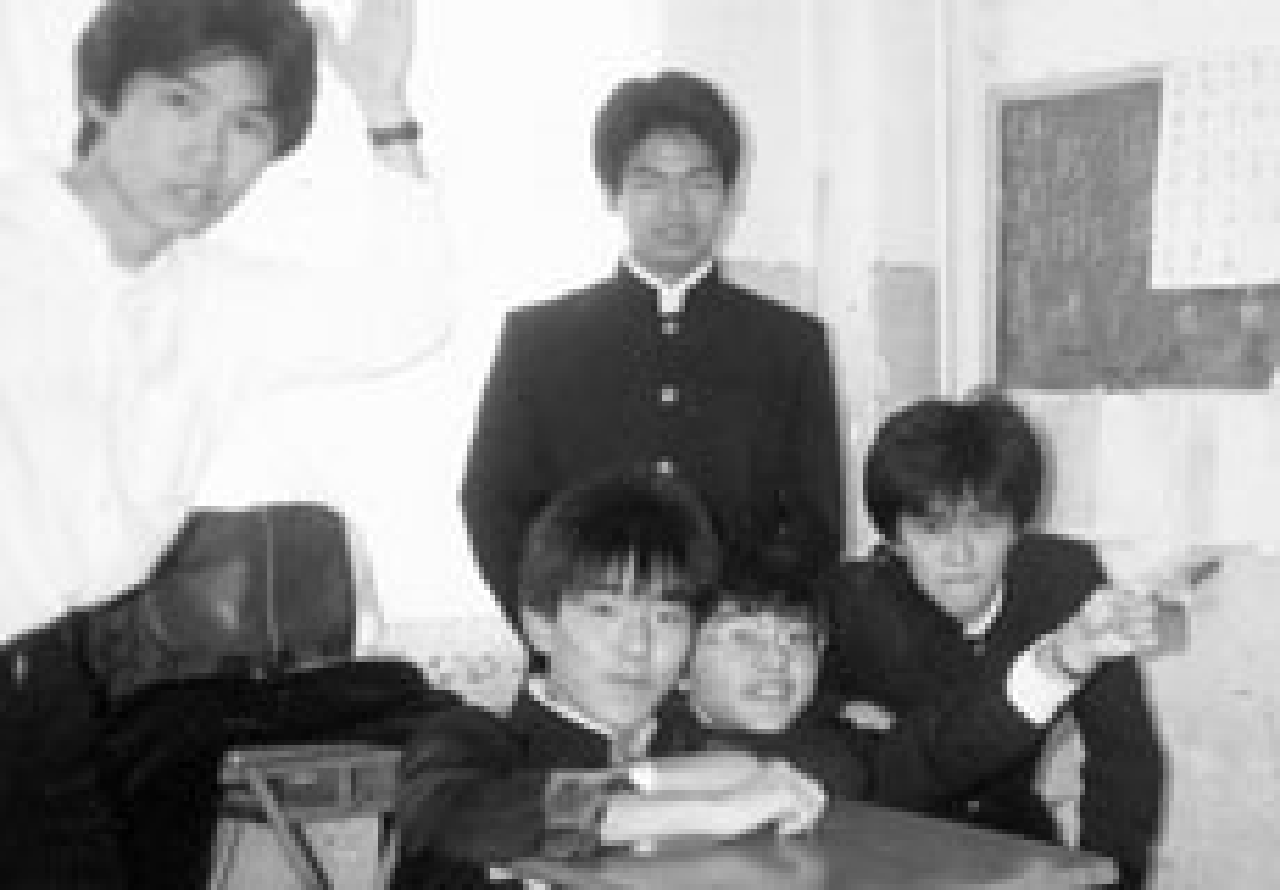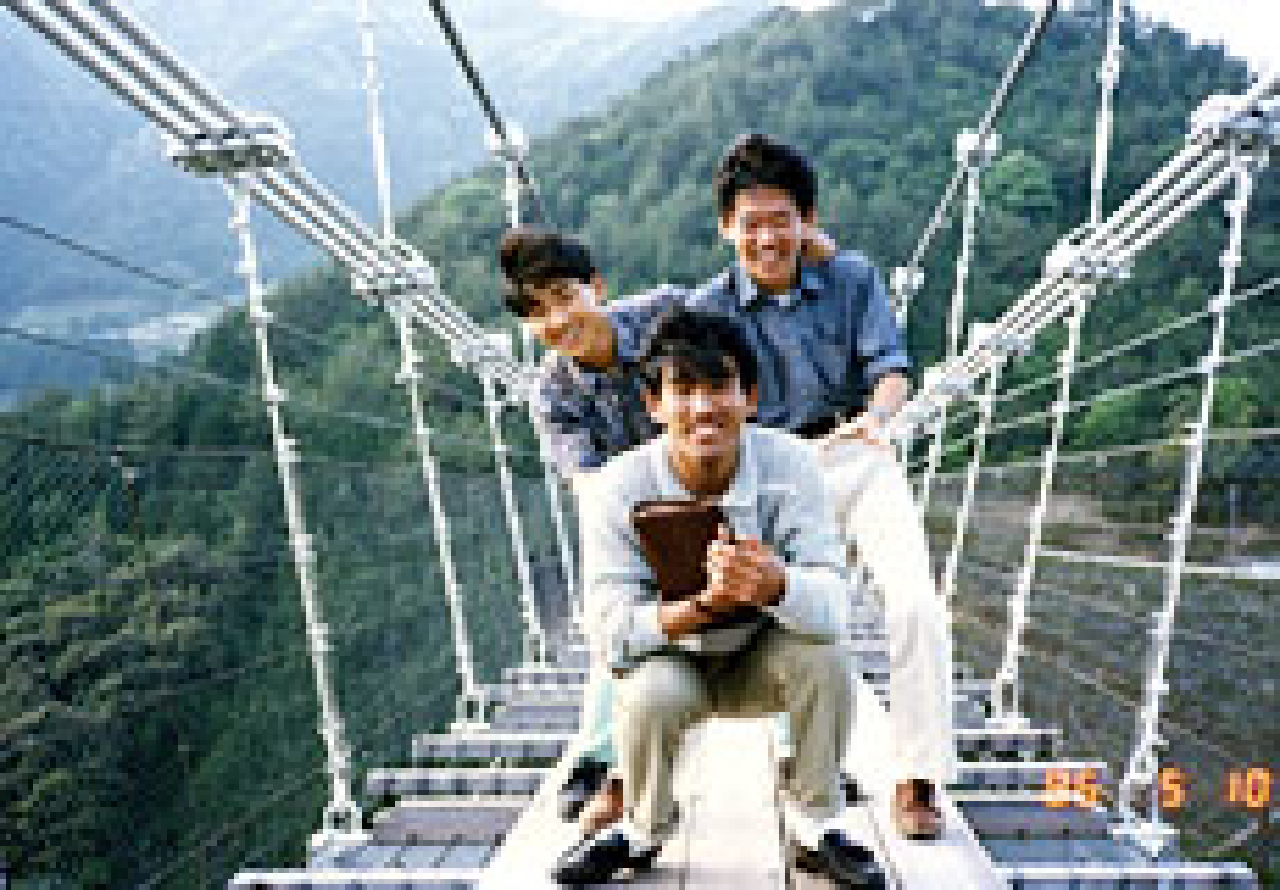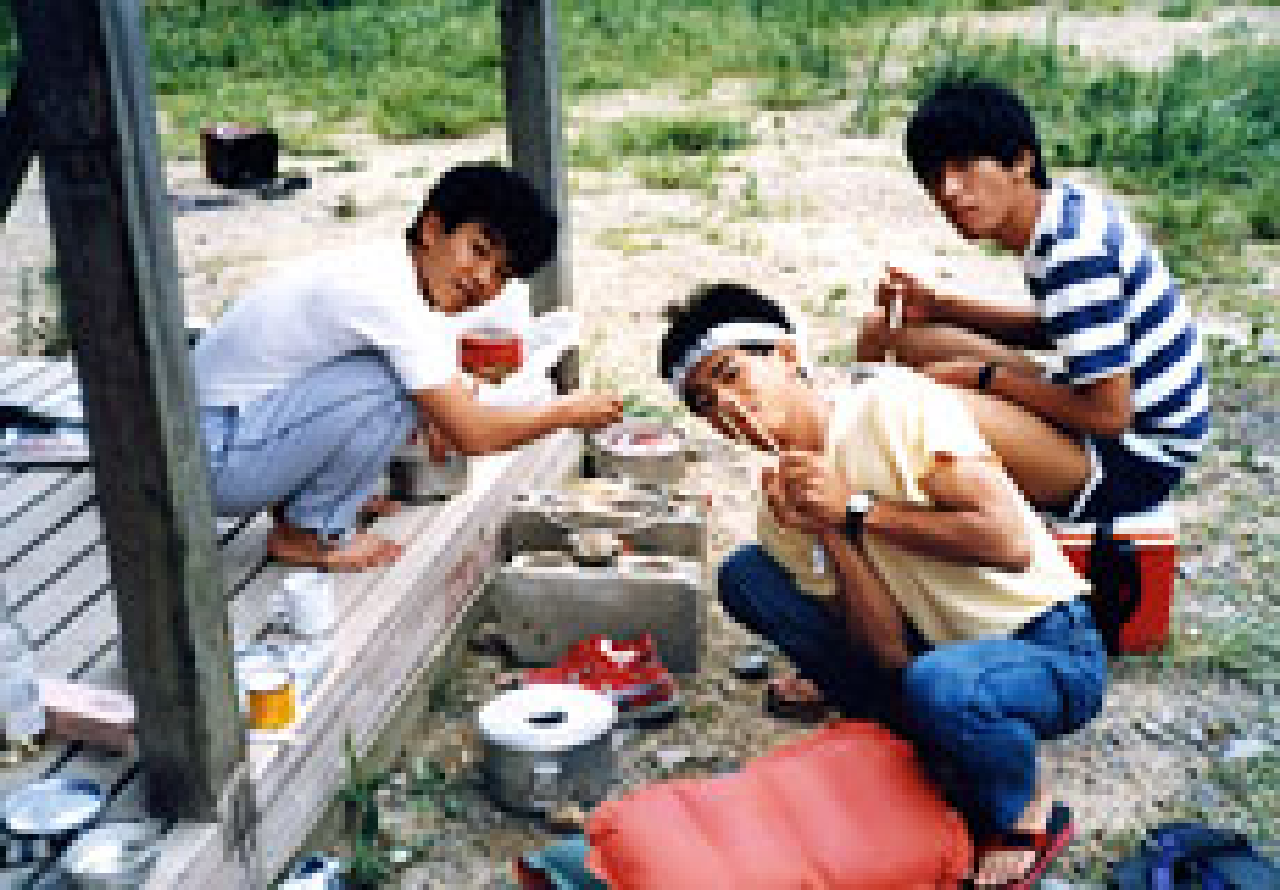大阪大学を卒業し、当時の主任科長、作田守教授に入局を許可していただき、矯正の勉強がはじまりました。しかし、待っていた現実は、学会準備のための郵便物の発送とコピー取りの毎日でした。
夏を過ぎ、大学の同窓会をしたところ、特に開業医に就職した人は臨床家として成長していました。学生時代ぱっとしなかった人が、歯を抜けるようになったと聞いたときにははっきり言ってショックでした。私ができるのは、コピー取りだけです・・・。焦る思いを抑え、矯正の勉強をしました。
学会も無事終わり、以降本格的に矯正を学びました。いろいろな立派な先生方にアドバイスを受け、研修させていただきました。そして、5年が経過し、臨床経験数も増え、日本矯正歯科学会認定医も取得することができました。その後は恩返しとして、学部6年制の先生方の臨床指導、卒業2年目までの先生方への臨床指導をおこないました。
大学病院にて矯正治療を勉強しておりましたが、一般歯科治療の勉強も、開業医の先生の元で約5年間行っておりました。しかし、週に数回の研修ですのでそれ程大した腕はありません。そのためか、余裕がなく、カルテがたまり、焦って患者様への説明もそこそこになってしまいます。精一杯がんばってきましたが、どうもしっくりきません。なぜなのだろうか?それは、自分の一般歯科治療能力の低さと現在の保険医療制度にあると考えました。
自分の一般歯科治療能力は、研修により鍛えられます。しかし、現在の保険医療制度はどうすることもできません。保険は、どれだけ丁寧にしっかり治療したかが評価されなく、画一的な評価です。丁寧にしっかり治療すればするほど赤字になってしまいます。患者様には喜んでいただいても、従業員、家族を支えられない気がしました。
それならば、私のもっとも得意とする矯正治療専門で開業しようと決断しました。幸い、各分野の第一線で活躍している先輩、同級生がたくさんいましたので、チーム医療体制を取ろうと決めました。ちなみに矯正科同期入局者は6人でしたが、現在矯正専門で開業しているのは3人です。
開業する段階でもう一つの取り組みとしたのは、矯正治療に伴う総合的な美容を意識するという事でした。矯正治療は子どものうちに行う場合、男女の差はほとんどなく、本人よりもむしろ保護者の方がお子様の歯並びを気にして連れて来られます。仕事などの事情もあると思いますが、大抵の場合はお母さんに連れられて医院を訪れます。
そして大人の矯正治療では、そのほとんどが女性の方です。驚いたことに男性の方は成人の矯正治療というものに無関心な場合が多く、矯正治療は子どもの内にしておくものだと思っている人もいるのです。歯並びが及ぼす悪影響についての認識というのもあまりないようなのです。それに比べると女性の方はコンプレックスや美意識が男性よりも高く、積極的に矯正治療を受けようと考えている人が多いのです。子どもの頃は何らかの事情で矯正治療を受ける事ができなかったけど、自分で収入を得て、時間の都合も自分で判断できるようになり、矯正歯科を訪れる方が多く見受けられます。
また、女性の方は矯正に限らず美容に関して非常に興味が高くあり、それが実は機能的な役割を果たしているという事も自覚されているケースが多いことにも気づきました。そこで考えました。女性は自らの意識で行動し、よい影響をやがて自分の子どもにも反映させていくのでは?それならば女性の積極的な意識は子どもの矯正につながり、男性にも間接的な影響を与えることができるのではないか。矯正治療は歯の機能回復に大きく貢献するのですから、これはすばらしい事です。
そこで私が目指したのは女性にとって、また子どもにとっても抵抗感なく矯正治療のメリットを示すことが出来る医院作りでした。コンセプトは「より美しく機能的に」そう考え、1999年の開業に至るまで、患者さんが心地いいと感じてもらえる医院の建物や対応、矯正治療や医院スタッフの意識統一をどう進めるかを考えました。
そして開業10年目の2008年初頭、矯正治療に関する経験・実績・専門知識が認められ、日本矯正歯科学会専門医試験に合格しました。しかし医療技術は日々進化しています。これからも鍛錬・研究を怠らず、また患者様や地域に貢献でき、信頼されるクリニックを目ざし続けています。